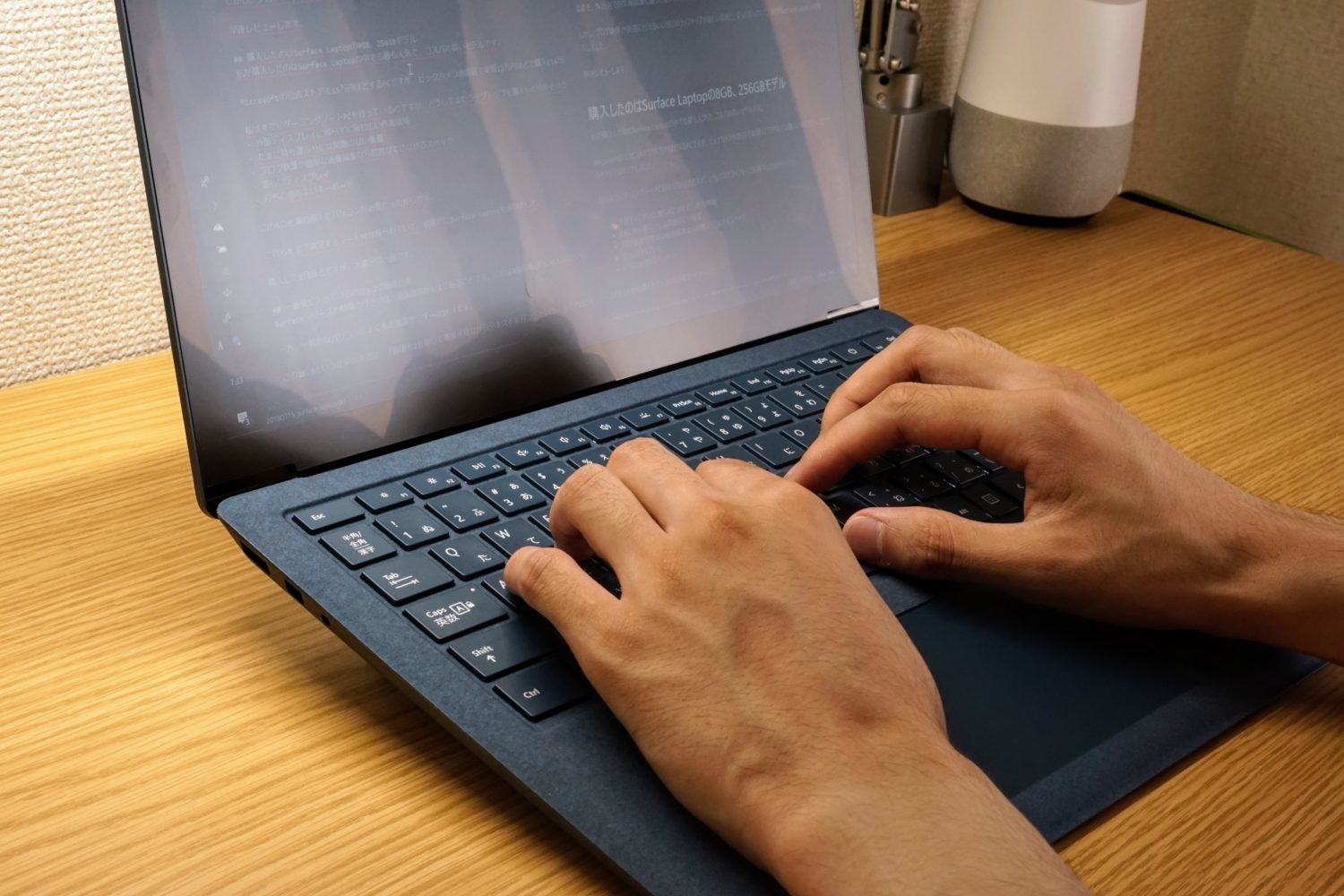Surface Goの日本国内価格に避難殺到中です。
相変わらずOfficeを抱き合わせにしているせいで、Officeを必要としない方にとっては「高い」と感じるのは当然です。
私もその一人ではありますが、そもそもSurface Goをそこまで求めていません。
というのも、10インチのPCを使っていて一番気になるのが作業領域の狭さなので、サイズ的にマッチしません。
また、Pentium搭載のWindowsというのは動作の快適性でかなり不安ですよね。
なので、外出先での文章執筆に限った使い方であればChromebook C101PAで十分だと思っています。
しかし、ブログ執筆が快適に行えるいい感じのラップトップが欲しいなあと、ずっと思っていて、結局Surface Laptopを購入しましたのでレビューします。
目次
購入したのはSurface Laptopの8GB、256GBモデル
私が購入したのはSurface Laptopの中でも最も人気で、コスパの高いモデルです。

Microsoftの公式ストアで15万円ほどするPCですが、ビックカメラ池袋店で実質12万円ほどで購入(14万円+2万円のポイント)しました。
私はすでにゲーミングノートPCを持っているのですが、どうしてまたラップトップを購入したのかというと、
- 外部ディスプレイに頼らずに済む広い作業領域
- たまに持ち運ぶ分には問題のない重量
- ブログ執筆や簡単な画像編集なら問題なくこなせるスペック
- 美しいディスプレイ
- 打ち心地のよいキーボード
この5つを兼ね備えたパソコンが必要だったからです。
これらを全て満足するノートPCは限られていて、結果的にSurface Laptopを選びました。
購入して2日ほどですが、大満足の一品です。
一番気に入っているのは3:2の画面比率
Surfaceシリーズの特徴のひとつは、画面比率が3:2であることです。これはA版の紙(約1.4:1)に近い比率。
一方、一般的なパソコンによくある液晶モニターは16:9です。
この16:9という比率の欠点は、「画面を2分割して書類を見ながらテキストを打つ」という、多くの方が行うであろう作業のときに縦が狭くなってしまうことです。
動画を観るときには適しているんですけどね。
横書きの文書作成では、縦スクロールの頻度が少ない方が、作業がはかどります。
この点で、Surfaceの画面比率は使い勝手が良いのです。
ここで、15.6インチで16:9のノートPCとSurface Laptopの大きさを比較してみます。
比較対象は私が持っているOmen by HP 15という、15.6インチのノートパソコンです。

| Surface Laptop(3:2) | Omen by HP 15 (16:9) | |
|---|---|---|
| 画面サイズ(対角”) | 13.5インチ | 15.6インチ |
| 縦[cm] | 19.01cm | 19.43cm |
| 横[cm] | 27.17cm | 34.54cm |
表をみると、13.5インチのSurface Laptopと15.6インチのOmen by HP 15の縦の長さがほとんど変わらない事がわかります。
まさにこれがSurface Laptopを選んだ理由です。
縦方向にこのくらいの作業領域があれば、自宅で使う場合でも外部ディスプレイが必要ありません。
持ち運べる重さ
Surface Laptopの重量は1.25kgです。15.6インチモデルと同等の縦サイズを確保しながらこの重量なら、かなり軽いと思いませんか?
個人的には、常に持つ運ぶのであればPCは1kgを切って欲しいです。
しかしながら、13インチのノートパソコンを探している時点で重量1kg以下は厳しい。
(と思ったら選択肢はNECのHybrid ZeroかLG Gram、Zenbook 13など、そこそこありますね。)
1.25kgというと、13インチのMacbook Airよりも重く、Macbook Proよりは軽い重さ。
毎日持ち運びたい重量ではないです。持ち運ぶのは、カフェに長時間居座ってノマドワークするときくらいですかね。

それ以外の場合はChromebookかiPad Proを持ち出します。
バランスの取れたマシンスペック(RAM:8GB, 第7世代Core i5)
8GBのRAM、256GBのSSD、CPUは第7世代のCore i5というのは
1. 文書作成が主な用途ならメインPCとしても使える
2. 画像・動画編集をするような方でも、サブPCとしては最低限のスペック
という感じだと思います。
私は1と2の間くらいの使い方です。
ミラーレス一眼を持っているので、画像編集はします。でも編集はiPad Proで行っているので、パソコンは使ってないです。
しかしせっかくSurfaceを買ったので、もしかしたら今後Lightroomを使う事もあるかもしれませんね。
そうなってくると、ちょっとスペックに物足りなさを感じるときがやってくるでしょう。

Rawファイルのレタッチを行う前提であれば、上位モデルを選んだ方が良いです。特に、メモリは16GBは積んでおきたいところ。その分だけ価格は上がってしまいますが。
ちなみに、私が購入したモデルとRAM16GBのモデルの価格差は約12万円です。ちょっと高いですよね。
こうして比較してみると、Core i5・8GB・256GBのモデルはかなりコスパが良いです。
- i5, 8GB, 256GB: ¥158,544-
- i7, 16GB, 512GB: ¥280,584-
Pixel Senceディスプレイが非常に美しい
iPhoneやiPadの画面解像度に慣れてしまうと、15.6インチでフルHD(1920×1080)の解像度というのは粗く感じてしまいます。
その点、Surface Laptopの画面解像度は2256×1504で、フルHDを上回っています。
画素のきめ細かさを表現するPPI(Pixel Per Inch)こそ201 PPIで、iPad Proの264PPIには一歩及ばないのですが、解像度は十分高いです。
また、色の再現度も良好です。
色の再現性を示す色域にはsRGBという、IECが定めた規格があります。
sRGBをカバーする割合をsRGBカバー率というのですが、Surface Laptopはかなり健闘しています。
- iPad Pro: 95.80%
- Surface Laptop: 94.70%
sRGBカバー率とsRGBカバー比は違う値なので注意してください。(カバー比の方は、sRGB規格に限らずどの程度の色再現ができるかを示すため、100%を超える場合があります)[/aside]
sRGBでいうと、Surface LaptopもiPad Proも遜色ありません。
ただ、iPadやiPhoneに関しては、DCI-P3という、2010年に発表されたデジタルシネマ用の規格を採用しています。
DCI-P3は、sRGBよりも広い色域をカバーしているので、色再現性についてはiPadの方が優れていると思います。

出典:https://robots.thoughtbot.com/whats-new-in-wwdc-16-designer-edition
sRGBはDCI-P3と比べると赤と緑の再現性が低いです。
実際に、iPad ProとSurface Laptopで同じ写真を見比べると、より鮮やかに表示できているのはiPadの方だと感じます。

iPadの方が、桜のピンク色をよりキレイに表現できています。
Surface Laptopも十分キレイですけどね。
何時間でも触っていられるキーボード
Macbookを家電量販店で試すたび「薄いキーボードは割り切りが必要だなあ」と感じます。
購入してずっと使っていれば慣れるのかもしれませんが、やっぱり自分にはキーボードの深い打鍵感が必要です。
Surface Laptopのキーストローク(打鍵深さ)は1.5mmとノートパソコンとしては十分な深さを持っています。

特別高級感があるわけではないですが、タイピングのしやすさはノートパソコンの中でもピカイチです。
まとめ 「普通に使えるノートパソコン」ならSurface Laptopがおすすめ
以上、Surface Laptopのレビューでした。
Surface Laptopは、Surface BookやSurface Proのように際立った特徴があるわけでもない、ごく普通のラップトップパソコンです。
でも、タブレット全盛期にむしろこういった、普通のノートパソコンは貴重な存在。
35年以上もの間ずっと形を変えてこなかったラップトップ型のパソコンの最終型が、このSurface Laptopなのだと思います。
ノートパソコンを探している全ての人に、本当におすすめです。